口腔機能発達不全症になる原因
|
【目次】 ■口腔機能発達不全症 |
こんにちは!
ヨリタ歯科クリニック管理栄養士チームです!
11月に入り、朝と夜の冷え込みが増してきましたね。
冬用の布団やひざ掛けなどを使い始めた方も、多いのではないでしょうか。
寒くなると体調を崩しやすい方もいらっしゃると思います。
体調管理には十分に気を付けてくださいね!

また、新型コロナウイルスの心配もあるなかで、
インフルエンザの流行も心配になる季節になってきました。
ヨリタ歯科クリニックでは、希望するスタッフに
インフルエンザワクチンの予防接種を行いました。

院長ブログでは、予防接種の様子も掲載しておりますので、
興味がある方はぜひ読んで頂けると嬉しいです(笑)。
予防接種を受けることも、感染を防ぐ手段の一つであるとは思いますが、
手洗い・うがい・十分な睡眠を心掛け、十分な栄養を摂取することで
感染を防ぎましょう!
10月の2週目のブログでは
「口腔機能発達不全症とプレスマクラブ」について、お話させて頂きました。
今月のブログでは「口腔機能発達不全症になる原因」について
詳しくお伝えしていきますね!
口腔機能発達不全症
口腔機能発達不全症はその名の通り、“口腔機能”が“発達不全”の状態です。
口腔機能とは、
■食べる機能
■話す機能
■呼吸する機能
のことを指します。

この口腔機能が十分に発達していない、
あるいは正常に獲得できていない状態を
口腔機能発達不全症と呼びます。
つまり、お口の成長が上手くいっていない状態となるのです。
これらの原因として、主に
➀乳児の頃の飲み方が、まだ残っている状態(乳児嚥下の残存)
②口呼吸
③低舌位
が挙げられます。
➀乳児の頃の飲み方が、まだ残っている状態(乳児嚥下の残存)
月齢は成長しているのに、
乳児の頃の飲み込み方が、残っている状態を指します。
乳児の頃の飲み込み方といえば、
授乳を想像してみると良いと思います。

唇同士は、重なることがなく
舌を前後に動かすことで、
食べ物(母乳)をのどの奥に運んでいます。
乳幼児は本来であれば、離乳食を通じて、
徐々に乳児嚥下から、成熟型嚥下(成人嚥下)に移ります。
成熟型嚥下(成人嚥下)の場合、
食べ物が外にでないよう、唇同士を重ね
舌を上下に動かすことで
食べ物をのどの奥に運んでいます。
しかし、いくつかの原因によって、
この成長が妨げられることがあります。
原因としては、母乳やミルクを飲んでいる状態から
離乳食を与える時期への移行が
段階的ではないことが挙げられます。
つまり、お子さんのお口の成長に
見合っていない離乳食の与え方は、
お口の成長にとって良くないのです。
一つ一つ、ステップを踏んで離乳食を与えることが、
お口の成長に必要なのです。
②口呼吸

鼻呼吸ができず、口で呼吸をしている状態を指します。
きちんと鼻呼吸ができず、口呼吸をする習慣があると、
舌の位置が低位になる「低位舌」になりやすいのです。
先程、成熟型嚥下(成人嚥下)でも少し説明しましたが
食べ物などを飲み込む時には、舌の上下運動をして
舌を上顎につけたまま、舌をうねらせる(ローリングといいます)ことで
食べ物などを、のどの奥に送っています。
低舌位になると、飲み込む時に、舌をうまく使う事ができない状態、
つまり、“飲み込む機能”の発達に悪影響が及びます。
③低位舌
低位舌は、口呼吸の習慣と高い関連性があります。
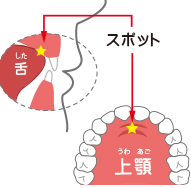
舌の置くポジションはとても重要であり、
常に、「舌の本来あるべき正しい位置=スポット」に
舌の先を置き、舌全体が上顎についていることが、大切です。
(スポットについては10月の2週目のブログを参考にしてみてください。)
また、低位舌は歯並びや、あごの発育、
さらには発音にも悪い影響を及ぼします。
上記のように、主に3つの原因が、あごの成長を妨げてしまい、
歯並びまでも悪くなってしまうのです。
口腔機能発達不全症と、口腔習癖との関連性
突然ですが皆さん
『口腔習癖』とは一体何なのか、ご存じでしょうか?
口腔習癖とは、日常的な生活の中で無意識に行っている、
口腔に関した習慣行動のことを意味します。
つまり、“お口に関する無意識に行ってしまう癖”ということです。
口腔習癖には
■指しゃぶり
■弄唇癖(唇を咬んだり、吸ったりする癖)
■舌突出癖(舌を前に出す癖)
■口呼吸
■口唇の閉鎖不全(お口ポカン)
■低位舌
■構音障害(舌足らずの発音)
■態癖(猫背、頬杖、寝る姿勢など)
などが挙げられます。
これらの習慣的な行動により、歯並びだけでなく、
あごの骨の形態や、口腔機能にも悪影響を及ぼします。
そして、口腔機能発達不全症には
様々な病態(病気の状態)がみられますが、
これらは全てバラバラな病態ではなく、関連性があります。
今回は、口腔習癖が原因となって、
様々な口腔機能発達に影響を及ぼし、
口腔機能発達不全症が、引き起こされる例をご紹介します。
例えば、代表的な口腔習癖である指しゃぶりをすると…

【指しゃぶり】
↓
【歯並び・咬み合わせに異常が生じ、不正咬合(開咬)になる】
開咬により、食べ物を噛む機能に悪影響が出ます。
(※開咬とは、歯を咬み合わせた時に上と下の前歯の間にすき間ができてしまい、
食べ物が噛み切れない状態を指します。)
↓
【舌の突出がみられるようになる】
食べ物を飲み込む時に、歯のすき間から舌を前に出す動きがみられ、
これは異常嚥下となります。
また、舌の突出により、さらに開咬を強めてしまうという
悪循環にもなります。
↓
【口呼吸、口唇の閉鎖不全となる】
開咬では口唇は閉じにくくなり、常に口を開いている口唇閉鎖不全になります。
口唇閉鎖不全で、常に口を開いているため、口で呼吸をする「口呼吸」になります。
↓
【低位舌になる】
口呼吸の気道確保のため、下顎を下方に下げるので、
舌は前方位で低位になります。
↓
【構音に障害が出る】
低位舌や舌突出癖では、発音時に舌が出やすくなり、
舌足らずの発音となる、「構音障害」がみられ、
構音機能が低下してしまいます。
次々に起こる低位舌、口呼吸、舌突出癖の口腔習癖が悪循環を作り、
口腔機能発達不全の、悪いスパイラルを作り続けてしまうのです。
このように、指しゃぶりという口腔習癖ひとつをとっても、
様々な病態が引き起こされ、どんどん悪循環になってしまうのです。
口腔習癖は指しゃぶりや
舌突出癖、口呼吸、低位舌だけではありません。
態癖といわれる頬杖、猫背や
食事時・睡眠時の悪い姿勢なども、密に関連しています。
■お子さんに、頬杖や猫背の癖は、ありませんか?
■地面に足を付けず、ぶらぶらした状態で、食事をしていませんか?
■うつぶせ寝や横向き寝の姿勢で、寝ていませんか?
これらの癖によって、「正しい呼吸」が、できないようになってしまいます。
「正しい呼吸」とは、鼻呼吸のなかでも、横隔膜を動かした「腹式呼吸」です。
足底がしっかりと地面につく姿勢をとると、正しい呼吸を行いやすくなります。
普段から足底を地面にしっかりとつけて、腹式呼吸を行いましょう。
食べる姿勢が安定すれば、咀嚼運動がスムーズに行われ、
唾液の分泌が盛んになります。

唾液分泌により、味わいも深く、消化にも良い食事となります。
美味しいと感じられれば、体だけでなく、心の健康にもつながります。
また、うつぶせ寝や横向き寝では、顔が圧迫され、口唇の閉鎖が困難となり、
口呼吸が誘発されやすくなります。

さらに、胸部の圧迫によって浅い呼吸となってしまいます。
できるだけ、仰向けで寝るように心がけましょう。
最後に
いかかでしたでしょうか。
「口腔機能発達不全症になる原因」について
なんとなく、お分かり頂けたでしょうか。
様々な口腔習癖が原因で、悪循環が引き起こされ、口腔機能の発達が妨げられてしまいます。
小児期である15歳頃までに、正しい口腔機能を獲得しなければ、
65歳以降である高齢期に、口腔機能の低下で悩む前に、
成人期に口腔機能を発揮することが、難しくなります。
小児期に口腔機能を獲得することは、生涯の健康寿命にも大いに関係するので、
現時点でしっかりと対策を行い、口腔機能を発達させることが、とても大切です。
一度、お子さんを観察してみてください。
もしかすると、「うちの子に当てはまる!」という方もいらっしゃるかもしれません。
「子どものお口の成長や癖で気になることがある…」と思われた方は、
ぜひヨリタ歯科クリニックで、相談してみてください。
次回のブログでは、
ヨリタ歯科クリニックの管理栄養士が考案した、
季節の食材を使ったメニューを掲載させて頂きます!
次回の更新も楽しみにしていてくださいね!
参考文献:子どもの咬合を考える会 不正咬合を予防する子育て10ヶ条
~新生児期・乳幼児期編~
:歯科衛生士 June 2019 ;43:20‐33
:口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方 (令和2年3月 日本歯科医学会)
<ヨリタ歯科クリニック 管理栄養士チーム>
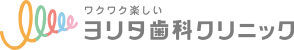




































































 初回予約はこちら
初回予約はこちら





























 採用情報
採用情報